
結論!「小規模な倉庫は建築物に該当しない」:基準総則・集団規定の適用事例2017年度版
建築確認申請における、全国的な取扱いのスタンダードである「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の2017年度版が発刊されま...
建築基準法のアレコレと管理人の趣味をどうぞ

建築確認申請における、全国的な取扱いのスタンダードである「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の2017年度版が発刊されま...

平成29年11月10日付けの技術的助言で、まずは共同住宅に限り、宅配ボックス等の設置部分が容積率から緩和されることになりました。まだ限定的ですが、今後は戸建住宅や事務所ビルなどにも適用範囲が拡大される見通しです。

10月23日から11月21日まで、パブリックコメントを募集している案件に以下のようなものがあります。 (クリックすると国交省のサイトに飛び...

建築基準法をもっと身近に感じ、理解を深める助けとなりそうな2冊の参考書を紹介します。

建築物の敷地が区域、地域、地区の内外にわたる場合については、すでにこちらの記事にまとめました。 この記事では、もっとシンプルに一覧...

特定避難時間倒壊等防止建築物であれば、すべて竪穴区画が必要になるのかどうか、確認してみましょう
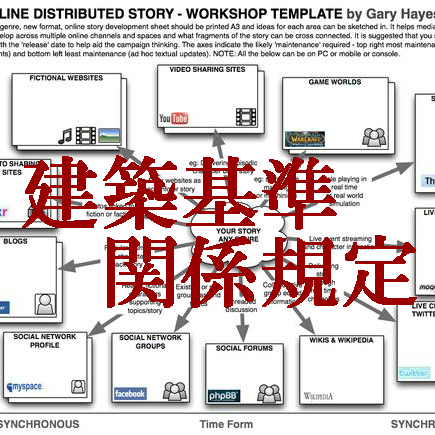
建築基準関係規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について 建築基準関係規定となっている、建築物のエネルギー消費性能の向上に関...

平成29年4月より、省エネ適判制度が施行されるのはみなさまご存知のとおりです。 省エネ適判制度や、建築物省エネ法に関する届け出については国...

小規模な倉庫について、国交省から技術的助言が出されてから早2年が経とうとしていますが、未だに特定行政庁ごとに取扱いが様々です。 現時点...
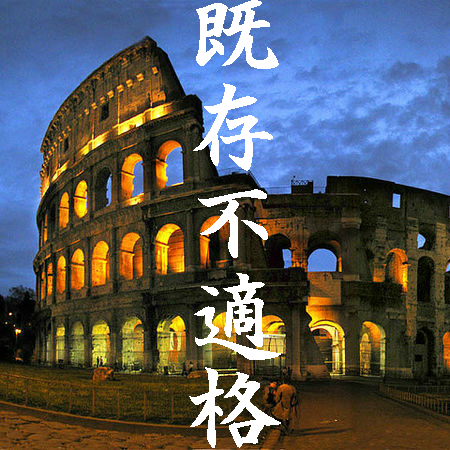
確認申請が必要な増改築、用途変更の計画が好きじゃない、避けている、見たくもないという方も少なからずいらっしゃると思います。 しかし、好き...

注:最新の令112条はこちらの記事でご確認ください。記事内の項ずれは適宜読み替えてください。ご不便をおかけしますがご了承ください。【2020...

注:最新の令112条はこちらの記事でご確認ください。記事内の項ずれは適宜読み替えてください。ご不便をおかけしますがご了承ください。【2020...
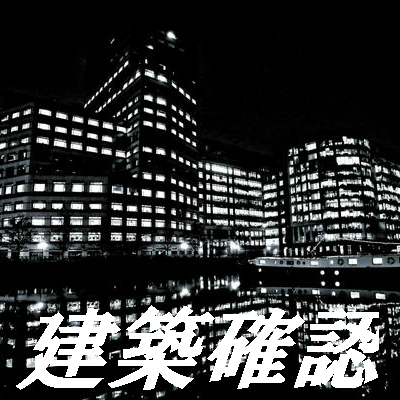
平成28年6月1日より建築基準法の改正に伴い、建築確認申請書の第四面の一部が変更になります ご存じの方も多いとは思いますが、平成28年...

平成28年6月1日施行の改正建築基準法について、ざっくりと簡単にまとめます。 建築確認の申請書4面が、同様に平成28年6月1日から新書...

採光上有効な開口部の検討を行っている際、ふと、ガラスブロックはどういう扱いなのか気になったので調べてみました。 当たり前の...

改正後の法第27条第1項と施行令、告示等の関連一覧防火避難規定の要、法27条の改正法が平成27年6月1日に施行されました。 これまでの法2...
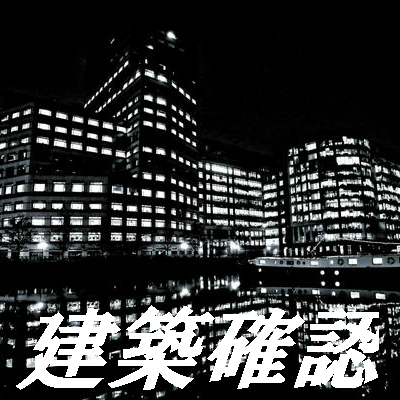
6月から改正法が施行され、申請書の書式も変わりました。 主な記載方法は下の記事でご確認いただくとして、今回はニッチに第6面についてのみ、注意...

平成27年6月の建築基準法の改正法施行により、確認申請関連の書式や書類にも影響があります。 確認申請書類は、新たな記載事項が追加にな...

平成27年6月1日より、改正建築基準法による確認申請手続きがスタートします。 特に、構造適判が絡む場合の申請の流れはこれまでとだいぶ勝手が...
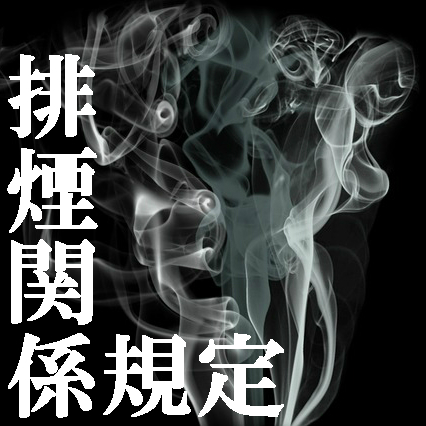
建築確認申請の法チェックで避けて通れない排煙チェック。 排煙設備の設置について、緩和規定を定めた、いわゆる「排煙緩和告示」が平成27年...

小規模な倉庫が建築物ではなくなりました!! ちょっと衝撃的な取り扱いが公表されました。 タイトルのとおり、小規模な倉庫を建築物とし...
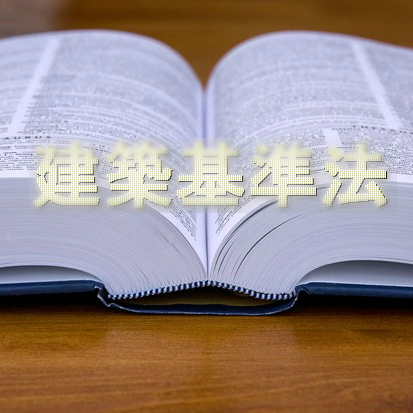
構造適判制度の運用が始まってからも、幾度と無く建築基準法の改正は行われています。 改正の度にしっかり内容を押さえていれば、特に過去を振り返...

平成26年7月1日に施行される改正施行令を再チェックしておきましょう 今年(平成26年)は建築基準法の大改正の年です。 木造準耐火、適判...
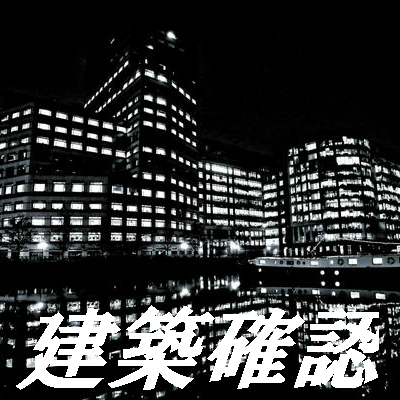
当サイトが今日もどこかで誰かの役に立っているかもしれないという実感 先日、下のメールをいただきました。 なんとありがたいメー...
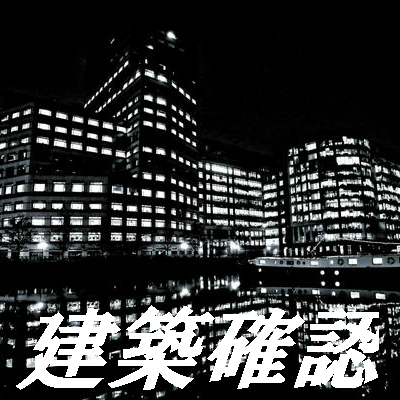
4月からの申請書変更を踏まえ、申請書の記入で間違いやすいポイントをチェック 以下の記事でも書いたように、天井脱落対策(特定天井)に関連して...
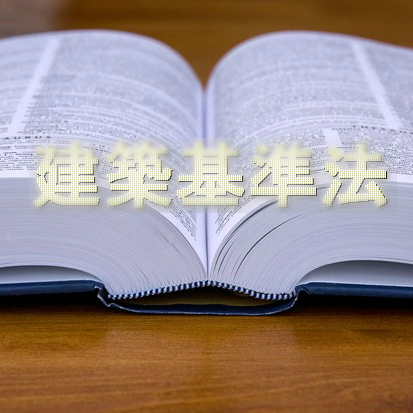
読者様からのご指摘により以下の3記事について修正しました。 無窓居室に必要な措置を逆引きで考えると意外とスッキリする 画像の中の記載...
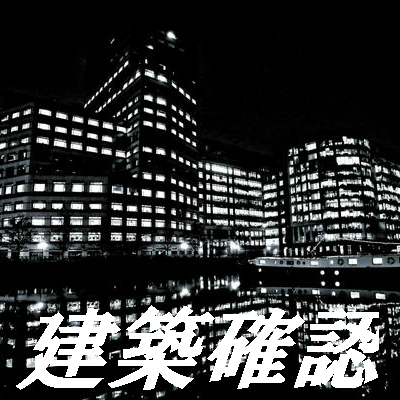
「建築」の定義について今さらながら確認 建築基準法により定義される「建築」行為の意味を、いまさらながらまとめてみます。 建築基準法 ...
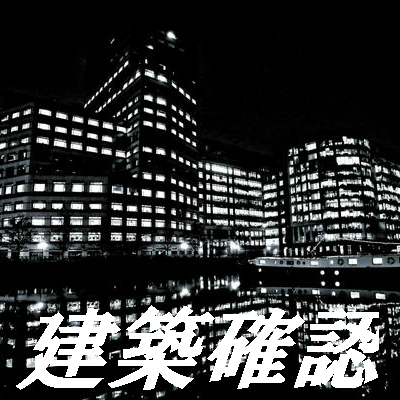
大規模の修繕と大規模の模様替の定義 修繕とは 修繕という言葉の意味合いは、3つの条件(要件)により成り立っていると考えられています。 ...
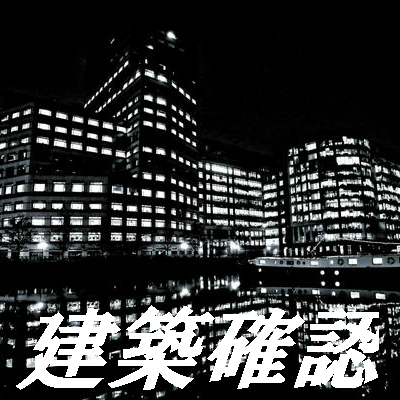
建築基準法の「居室」の定義は? 建築確認に必ずついて回る「居室」に関する条文。 その居室の定義をはじめ、居室についての情報をまとめてみた...
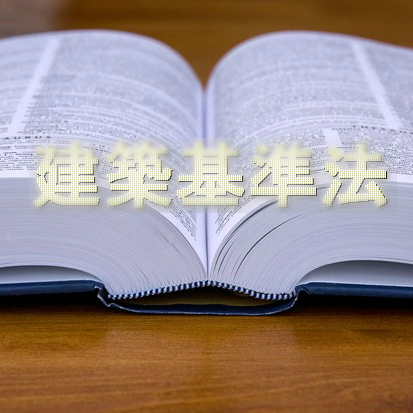
特殊建築物の種類 特殊建築物については建築確認 特殊建築物についてで簡単にまとめていますが、ここではもっと深く掘り下げて見たいと思います。...